本サイトでは、記事にアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を使用しています。
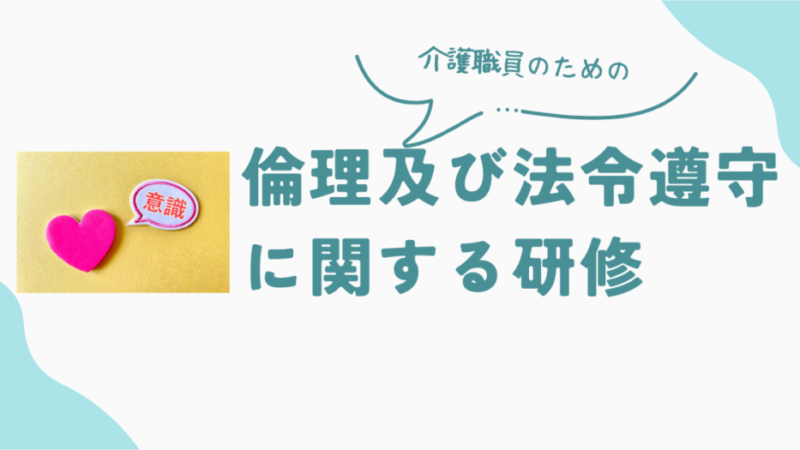
皆さん、こんにちは。福祉施設の研修講師「いし~ちゃん」です。
このブログでは、介護や福祉に携わる方に向けて、「短時間で好きな時間に分かりやすく学べる」をモットーに、研修内容や明日から使える介護・福祉に関する知識をご紹介していきます。
- 研修に使える資料がほしい
- 研修のポイントを知りたい
- パワーポイントに使える資料が欲しい
- 勉強したいけど、時間や費用はかけたくない
このブログを活用していただければ、勉強したいと思っている介護・福祉従事者の方はもちろん、研修を担当している方にとっても役立つ内容を得ることができます。
今回の記事では、「倫理及び法令遵守に関する研修」の内容をご紹介していきます。
研修資料はこちら➡「倫理及び法令遵守に関する研修」
「倫理及び法令遵守に関する研修」は、年度初めなど区切りの時期に行うことをおススメします。
特に4月は、新しい職員が加わる時期であり、また部署間の異動なども一番活発に行われる時期でもあります。法人の考え方や理念などの意識統一や職員が施設のミッションに対し、共通の認識を持って仕事に取り組めるように、ぜひ活用してください。
倫理とは
倫理とは何かを調べると以下のような内容が出てきます。
人倫の道。社会生活で人の守るべき道理。人が行動する際、規範となるもの。
日本国語大辞典より引用
これを分かりやすくまとめると以下のようになります。
- 法律を守ること
- 規則を守ること
- 組織の一員として、決まりごとを守ること
- 誰かの役に立てるよう、努力すること
どれも社会生活を送る上では、当たり前とされている内容となっています。
倫理の基本
倫理の基本として、私が意識すべきことは以下の5つです。
- ルールを守る:法律や省令、就業規則などに従うこと
- 人の役に立つこと:求められた仕事をすること、社会貢献すること
- 責任ある行動:役割を果たすこと、最後までやり遂げること
- 人として成長する:前向きな姿勢、自己研鑽、協力し助け合うこと
- コミュニケーション:相手の話を聞く、確認する、報告する、相談する
この5つを意識的に実践していくことで、倫理的な行動をすることができます。
なぜ、倫理の研修が必要なのか
倫理に関することは、社会生活を送る上では当たり前にできているはずのことです。
ただ、常に倫理的な行動ができるかというと、必ずしもそうではないのが人間です。
例えば、自転車が点字ブロックの上に置いてあったとしても、「急いでるから」「自分には関係ないから」と何も行動しないことってありますよね?
このように、人は時に倫理的でない行動をとってしまうものです。
- 人は感情で動くから:イライラしたり、疲れていたり、人は心身の状態により、感情が揺れ動く
- 意識を高く保つため:強い意識を継続するのは難しい、定期的な確認やふり返りが必要
- 組織の意識統一のため:組織としての倫理観を高める、同じ方向を向いて仕事をする
だからこそ、少しでも「倫理」ついて意識づけを行い、自分の行動をふり返りながら仕事をしていくことが必要になります。
倫理が乱れるとどうなるのか
では、倫理が乱れている状態では、どのようなことが起こるのか確認しておきましょう。
いくつかの具体例を紹介しておきます。
- 他人の事はどうでもいい。自分が良ければそれでいい。
- 嫌なこと、面倒なことは人に押し付け自分はやらない。
- 見つからなければ何をしてもよい。
- 嫌いな人や同僚・上司の悪口や愚痴を言いふらす。
- 誰にも迷惑掛けていないという理由でルールを守らない。
- 別に問題ないので法律を守らない。
- 自分の思い通りにいかないことには、強い口調や態度・暴力により訴える。 など
介護現場で倫理が乱れる要因
介護現場を想像していただくと分かりやすいと思います。
- 常に人手不足
- 認知症の方の対応
- 不規則な勤務形態
- 業務に追われる毎日
介護現場は、いつもバタバタしており、業務に追われています。このような状況下で常に平常心を保つことは難しいです。
倫理の乱れは「言葉遣い」に表れやすい
倫理の乱れが一番表れるのが「言葉遣い」です。
- ご利用者に対する乱暴な言葉遣い
- 「早くして!」「なんで出来ないの?」
「動かないでって言ったよね」
「さっきもトイレ行ったじゃん!」など
- チームワークを乱す言葉遣い
- 「前にも教えたよね!」
「あいつのせいで…」
「せっかくやってあげたのに」
「なんで私ばっかり…」など
皆さんの職場では、このような言葉が飛び交っていませんか?
あなた自身がこのような言葉遣いになっていませんか?
ぜひこの機会にふり返ってみてください。
介護職に求められる「倫理観」について
世間からの介護職員からのイメージはどうでしょうか?
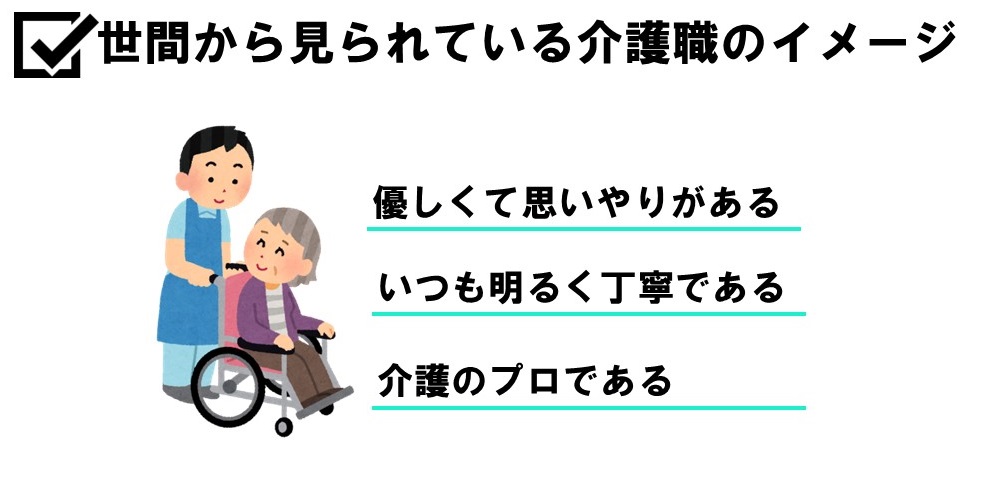
- 優しくて思いやりがある
- いつも明るく丁寧
- 介護の専門職(プロ)である
ご家族などから「介護の人はすごい、私にはできない、尊敬する」などと言われたことはありませんか?
世の中の目は、あるいは実際に施設入所されている方のご家族は、介護職に対して感謝・尊敬を向けられています。
実際の介護現場はどうですか?
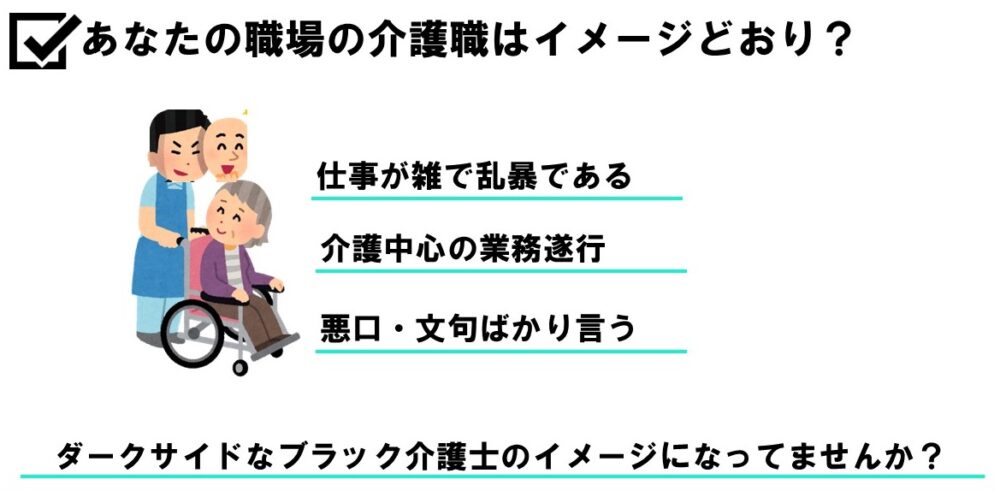
- 仕事が雑で乱暴である
- 介護中心の業務遂行
- 悪口や文句が溢れている
感情のまま不満や文句を言いふらし、ご利用者を物のように扱っているダークサイドブラック介護士になっていませんか?
介護職員には介護職員としての倫理観が求められていることを意識しておく必要があります。
介護福祉士の「倫理綱領及び行動規範」
介護福祉士会から出されている「介護福祉士の倫理綱領及び行動規範」を確認しておきましょう。
- 利用者本位・自立支援
- 専門的サービスの提供
- プライバシーの保護
- 総合的なサービスの提供と積極的な連携・協力
- 利用者ニーズの代弁
- 地域福祉の推進
- 後継者の育成
公益社団法人日本介護福祉士会「倫理綱領」
公益社団法人日本介護福祉士会「行動規範」
この機会に一度、目を通しておきましょう。
介護職員の責務
介護のプロとして、より質の高いサービスを提供することが、私たち介護職員の責務です。
だからこそ、一般的な倫理観と併せて、介護職員として倫理観を持った行動が必要になるのです。
介護のプロとしての倫理観を持ち合わせず、一般的な倫理観のみでは、一般の方が介護を行うのと変わらなくなってしまいます。
具体的には、介護福祉士会の倫理綱領及び行動規範に従ってケアを実践していくこと、それが介護のプロとしての責務につながっていきます。
まとめ
今回は、介護職員の倫理について解説してきました。
介護職員は一般的な倫理観と併せて、介護職員としての倫理観が必要になります。
毎日の忙しい業務の中、つい疎かになってしまう倫理ですが、この研修をきっかけに一度自分自身の介護や事業所の在り方についてふり返ってみてください。