本サイトでは、記事にアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を使用しています。
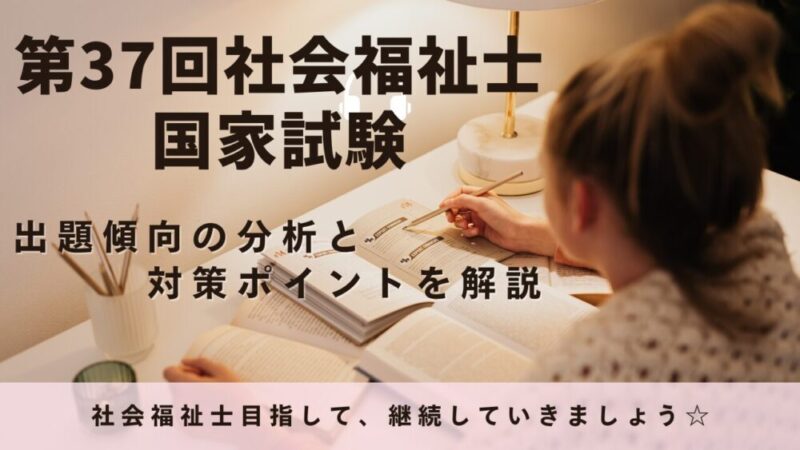
皆さん、こんにちは。社会福祉士の石井雄樹です。
このブログでは、介護や福祉に携わる方に向けて、「短時間で好きな時間に分かりやすく学べる」をモットーに、研修内容や明日から使える介護・福祉に関する知識をご紹介していきます。
- 研修に使える資料がほしい
- 研修のポイントを知りたい
- パワーポイントに使える資料が欲しい
- 勉強したいけど、時間や費用はかけたくない
このブログを活用していただければ、勉強したいと思っている介護・福祉従事者の方はもちろん、研修を担当している方にとっても役立つ内容を得ることができます。
今回は、新カリキュラムになって初めての社会福祉士国家試験の内容を分析していきます。
この記事では、第37回試験の出題傾向を振り返り、共通科目・専門科目ごとの特徴、そして今後の学習へのアドバイスをまとめています。これから受験を目指す方にとっても、今後の学習の指針となる内容ですので、ぜひ参考にしてください。
出題傾向の分析
難易度の高い「調整問題」の減少
例年、受験生の得点調整を目的とした非常に難解な問題が含まれていますが、今回はその割合がやや減少しました(前回:約20% → 今回:約15%)。
その一方で、事例形式や新しい出題形式に戸惑った受験生も多く、全体的な難易度が下がったとは一概に言えません。
同一テーマからの複数出題
「精神保健福祉法の入院形態」「レジリエンス」「障害者差別解消法」など、同じキーワードが複数の問題で問われる傾向が見られました。基本的な知識を深く理解し、複数の角度から問われても対応できるようにしておくことが重要です。
事例問題の増加
今回の試験では、事例形式の問題が全129問中48問と、全体の3分の1以上を占めました。事例問題は、実践的な判断力や応用力が求められるため、日頃から多様なケースに触れ、対応力を養うことが必要です。
共通科目の分析とポイント

医学概論
出題内容の概要: 人体の基本的な構造や機能、主要な疾病の特徴と予防法などが問われます。
分析とポイント: 例年の出題傾向から変化し、リハビリテーションやICF(国際生活機能分類)などの定番テーマが出題されず、代わりに「薬害有害事象」や「経皮的酸素飽和度(SpO2)」といった医学用語が問われました。基本的な医学知識を幅広く学習し、専門用語にも慣れておくことが重要です。
心理学と心理的支援
出題内容の概要: 心理学の基本理論、心理的支援の方法、心理療法の種類や特徴などが問われます。
分析とポイント: 事例問題が含まれたものの、基本的な出題が中心でした。特に、認知行動療法などの心理療法の特徴を理解していれば、得点しやすい科目でした。事例形式の問題に慣れ、落ち着いて問題文を読むことが大切です。
社会学と社会システム
出題内容の概要: 社会構造や社会変動、家族や地域社会の機能、社会問題の現状と対策などが問われます。
分析とポイント: 新カリキュラムによる内容変更がありましたが、基本的な知識で対応できる設問も多く見られました。一方、過疎地域の現状について具体的な数値データを問う問題もあり、統計データの理解も必要です。
社会福祉の原理と政策
出題内容の概要: 社会福祉の基本理念、歴史的変遷、福祉政策の立案・実施過程などが問われます。
分析とポイント: 他科目と内容が重なる出題が多く、横断的な理解が求められる科目です。例えば、「福祉の措置」や「福祉事務所」など、他科目でも取り上げられるテーマが出題されました。広範な学習と、各科目間の関連性を意識した学習が重要です。
社会保障
出題内容の概要: 社会保険、社会福祉、公的扶助、公衆衛生など、社会保障制度全般に関する内容が問われます。
分析とポイント: 事例形式の問題が増加し、「家族の現状と適用される社会保障制度」を問う問題が見られました。難易度にはばらつきがありましたが、過去問と類似した歴史問題も含まれており、基本的な学習をしっかり行っていれば対応可能でした。
権利擁護を支える法制度
出題内容の概要: 成年後見制度、虐待防止法、障害者権利条約など、権利擁護に関する法制度が問われます。
分析とポイント: これまで成年後見制度に偏っていた出題が、他の法制度にも広がりを見せました。また、「1から4までの記述はいずれも不適切である」といった新しい出題形式も登場し、幅広い法制度の理解と柔軟な思考が求められました。
地域福祉と包括的支援体制
出題内容の概要:地域福祉の理念、地域福祉計画、生活支援体制整備事業、重層的支援体制整備事業、関係機関との連携などが問われます。
分析とポイント:統計や実施状況に関するデータをもとに判断する問題が多く、深く考える必要がある設問が目立ちました。特に、制度の名称や内容が似ている問題が続いたことで、混乱した受験生もいたかもしれません。
今後は、制度の概要だけでなく、実施状況や自治体の取り組みなどの具体的な数値や最新情報にも目を通すことが対策のポイントです。難しさはありましたが、正確な知識を持っていれば十分対応できる内容でした。
障害者福祉
出題内容の概要:障害者の生活支援、障害者総合支援法、障害者差別解消法、各種福祉サービスの仕組みなどが問われます。
分析とポイント:出題内容には若干の偏りがあったものの、基礎知識で対応できる設問が多く、比較的得点しやすい内容でした。ただし、複数の白書を読み比べるような設問もあり、全体像を把握する力が求められました。
刑事司法と福祉
出題内容の概要:更生保護制度、医療観察法、犯罪被害者支援、矯正教育や福祉的支援との連携などが問われます。
分析とポイント:社会福祉士試験では新しい領域ですが、基本的な知識をおさえていれば対応可能でした。問題の中には過去問で類似したテーマもあり、3~4点は取れる構成だったといえます。
ソーシャルワークの基盤と専門職
出題内容の概要:社会福祉士の専門性、倫理原則、職業としての責任と実践原理などが問われます。
分析とポイント:例年通りの構成でしたが、一部の設問では詳細な倫理理論を問われる内容もありました。テキスト外の人名や考え方が登場することもあり、すべてを網羅するのは難しいため、取捨選択が重要です。
ソーシャルワークの理論と方法
出題内容の概要:ソーシャルワークの各アプローチ(課題中心・ナラティブなど)、面接技法、ケースワークやグループワークの展開過程などが問われます。
分析とポイント:事例問題が多く、選択肢に確信を持ちにくい設問も見られました。理論と実践の対応関係を理解し、事例の中にどのアプローチが含まれているのかを見抜く力が求められました。
社会福祉調査の基礎
出題内容の概要:社会調査の手法、調査票の作成、データの収集と分析、倫理的配慮などが問われます。
分析とポイント:新カリキュラムによる出題内容の追加は少なく、従来通りの範囲が中心。事例形式になることで選択肢の検討がしやすくなり、全体的には取り組みやすい内容でした。
専門科目の分析とポイント

高齢者福祉
出題内容の概要:高齢者を取り巻く課題、介護保険制度、施設・在宅サービス、地域包括ケアなどが問われます。
分析とポイント:出題数が減少し、介護技術の出題も消失。例年通りの問題もありましたが、法律の「制定」と「施行」に関する正確な理解が求められる場面もありました。
児童・家庭福祉
出題内容の概要:児童福祉法、児童相談所の役割、里親制度、家庭支援施策、困難女性支援法などが問われます。
分析とポイント:法改正に関連する設問が目立ち、制度名の混同によるミスが起きやすい内容でした。関係機関の役割をしっかり整理して学習することが重要です。
貧困に対する支援
出題内容の概要:生活保護法、生活困窮者自立支援制度、就労支援、居住支援、社会的孤立の防止などが問われます。
分析とポイント:難易度は低め。生活保護だけでなく、生活困窮者支援制度の比重が高まっており、今後の出題にも影響しそうです。
保健医療と福祉
出題内容の概要:地域包括ケア、医療と介護の連携、医療計画、緩和ケア、災害時の医療福祉連携などが問われます。
分析とポイント:事例形式が中心で、過去の頻出テーマ(医療計画など)が出題されませんでした。ガイドラインや最新の政策動向も押さえておきたい内容です。
福祉サービスの組織と経営
出題内容の概要:社会福祉法人、経営管理、サービス評価、第三者評価、人材育成やリスクマネジメントなどが問われます。
分析とポイント:タクソノミーI型の問題が減少し、難易度がやや上がった印象。複数の知識を組み合わせる事例形式が増え、読み取りと判断のスキルが求められました。
勉強を進める方へのメッセージ

社会福祉士国家試験は、毎年出題傾向に変化が見られます。ただ暗記するだけでなく、実際のケースにどう当てはめるかという「応用力」「実践力」がより重視されています。
これから受験を目指す皆さんには、次の3つを大切にしてほしいと思います。
- 過去問で基本と出題形式に慣れる
法改正や制度変更などの最新情報を押さえる
事例問題に取り組み、現場感覚を養う
そして何より、自分のペースで、毎日少しずつ積み重ねることが一番の近道です。
まとめ
第37回社会福祉士国家試験は、事例問題の増加や出題テーマの変化が見られましたが、基本を丁寧に押さえていた方にとっては得点のチャンスも多い構成でした。
試験は「社会福祉士として、実際にどう判断し、どう行動するか」を見られる場でもあります。知識と実践をつなげる力を養いながら、これからの学習に活かしていきましょう。
合格を心から応援しています!