本サイトでは、記事にアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を使用しています。
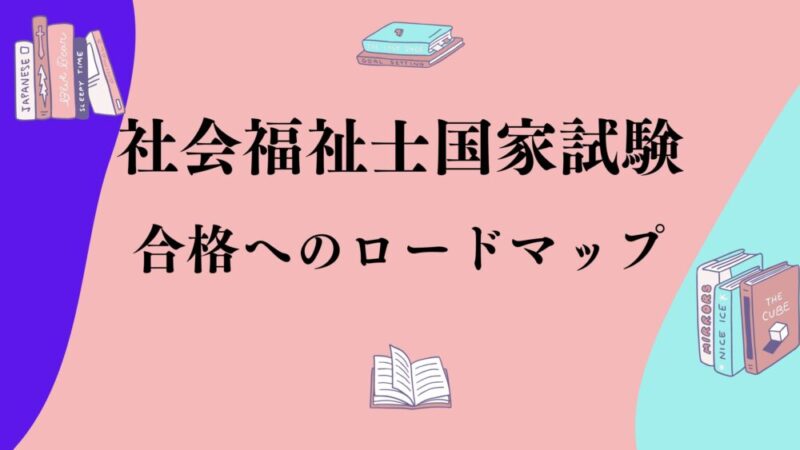
こんにちは、社会福祉士のいし~ちゃんです。
社会福祉士国家試験、合格したいけど何から始めればいいかわからない…そんなあなたに朗報!
この記事では、4月から始める社会福祉士国家試験合格のための最強ロードマップをご紹介します。
過去問の活用方法や、モチベーション維持のコツなど、合格するために必要な情報が満載です。
4月から勉強を始めようと考えているあなたは、かなり合格への意欲が高い方です。今から勉強を始めれば99.9%合格を掴み取ることができるでしょう。
社会福祉士国家試験とは

社会福祉士は、いわゆる「ソーシャルワーカー」と呼ばれる社会福祉専門職で「相談援助のプロ」です。
国家試験では、社会福祉士として実際に適切な相談援助ができるよう、幅広い知識やスキルを問う問題が出題されます。
社会福祉士国家試験の出題範囲(旧基準)
社会福祉士国家試では、様々な分野から出題されます。具体的には19科目とかなりボリュームのある内容です。
他の福祉系の資格である「介護福祉士」や「精神保健福祉士」よりも広い範囲となっています。
また「共通科目」と「専門科目」に分かれており、「共通科目」が午前中、「専門科目」は午後から試験が実施されます。
具体的な科目群と出題内容は以下の表をご確認ください。
| 共通科目 | 試験内容 |
|---|---|
| 1.人体の構造と機能及び疾病(7問) | 人体の構造、成長、発達や健康観や国際生活機能分類(ICF)などの知識 |
| 2.心理学理論と心理的支援(7問) | 相談援助に係る人間の心理についての知識や各種セラピー、心理検査 |
| 3.社会理論と社会システム(7問) | 社会学理論や社会構造に関する知識 |
| 4.現代社会と福祉(10問) | 福祉の原理や理想についての知識 |
| 5.地域福祉の理論と方法(10問) | 地域福祉の理解 |
| 6.福祉行財政と福祉計画(7問) | 行政の福祉の仕組みや福祉計画・国、地方の福祉の予算 |
| 7.社会保障(7問) | 社会保険・年金の歴史や知識 |
| 8.障害者に対する支援と障害者自立支援制度(7問) | 障害に関する福祉制度の知識 |
| 9.低所得者に対する支援と生活保護制度(7問) | 生活保護制度の知識 |
| 10.保健医療サービス(7問) | 現在の医療保険や医療法、地域での保健活動の知識 |
| 11.権利擁護と成年後見制度(7問) | 人権や民法における財産などの権利や成年後見制度の知識 |
| 専門科目 | 試験内容 |
|---|---|
| 12.社会調査の基礎(7問) | データの集計方法や基礎知識 |
| 13.相談援助の基盤と専門職(7問) | 相談を受ける際の基礎や過去の発展 |
| 14.相談援助の理論と方法(21問) | 実際の相談場面を想定した技術の習得 |
| 15.福祉サービスの組織と経営(7問) | 福祉の団体や組織の経営について |
| 16.高齢者に対する支援と介護保険制度(10問) | 超高齢化社会の現状や介護保険制度、後期高齢者医療制度について |
| 17.児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度(7問) | 児童虐待やひとり親家庭の支援、児童福祉法などに関する知識 |
| 18.就労支援サービス(4問) | 就労支援サービスは障害者雇用や労働法について |
| 19.更生保護制度(4問) | 更生保護制度は医療観察法、司法福祉について |
このように見てみると、正直ビビッてしまいますよね。でも大丈夫です。きちんと計画的に勉強をしていけば、必ず合格できる試験です。
社会福祉士国家試験の合格基準
社会福祉士の試験は1問1点、総得点150点で構成されており、正答率60%(150問中90問程度)の問題を正解できるかが合格の目安となっています。
そして、すべての科目群で得点をしなければなりません。つまり、0点の科目があると不合格になります。
過去の合格点と合格率は以下のとおりです。
| 第34回(令和3年度) | 第35回(令和4年度) | 第36回(令和5年度) | |
|---|---|---|---|
| 合格点 | 105点 | 90点 | 90点 |
| 合格率 | 31.1% | 44.2% | 58.1% |
令和6年度からの新カリキュラム(出題基準)
令和6年度から社会福祉士国家試験の出題範囲が新カリキュラムとなります。
以下の内容を確認してください。
試験科目
(共通科目)
① 医学概論
② 心理学と心理的支援
③ 社会学と社会システム
④ 社会福祉の原理と政策
⑤ 社会保障
⑥ 権利擁護を支える法制度
⑦ 地域福祉と包括的支援体制
⑧ 障害者福祉
⑨ 刑事司法と福祉(共通科目へ追加)
⑩ ソーシャルワークの基盤と専門職(専門科目だけでなく、共通科目にも追加)
⑪ ソーシャルワークの理論と方法(専門科目だけでなく、共通科目にも追加)
⑫ 社会福祉調査の基礎(共通科目へ)
(専門科目)
⑬ 高齢者福祉
⑭ 児童・家庭福祉
⑮ 貧困に対する支援(生活保護関連等が共通科目から専門科目へ)
⑯ 保健医療と福祉(保健医療関連等が共通科目から専門科目へ)
⑰ ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)
⑱ ソーシャルワークの理論と方法(専門)
⑲ 福祉サービスの組織と経営
勉強をする内容としては大きく変わりありませんが、専門科目だけを受験するという方は注意が必要です。
詳しくは、社会福祉振興・試験センターのホームページをご確認ください。
社会福祉士国家試験の勉強方法
それでは、社会福祉士国家試験に合格するための勉強方法について解説していきます。
4月に勉強を始めた場合のロードマップを解説していきますが、4月以降でもこのロードマップを参考にしながら勉強できるように作成していますので、ぜひご活用ください。
ステップ①:基礎知識を固める(4月~6月)
まず、基礎固めに取り掛かります。
と言っても、あの膨大なテキストを最初から読み込む必要はありません。
結論から言うと、いきなり過去問から取り掛かりましょう。
最初は正答を導くことが難しいと思います。しかし、過去問に触れることで、試験に出やすい項目や出題方法などを把握することができ、重要ポイントを押さえながら勉強を進められるため、とても効率が良いのです。
苦手分野・得意分野の把握もできますので、その後の勉強効率がどんどんアップしていきます。
- 過去問による基礎固め
- 過去問を解く(見る) ➡ 解答を見て問題を理解する ➡ 参考書等で確認する
この工程をくり返し行いましょう。
この基礎固めの時期では、何問正解できたかよりも、問題の文章や解説を理解する方がはるかに重要です。問題が解けなくて不安になるかもしれませんが、この時期なら全く問題ありません。
どんどん過去問に挑戦しましょう。
ステップ②:実践演習で力を伸ばす(7~9月)
4月~6月まで基礎固めに取り組んでいれば、正解を導き出す力もある程度身についてきているはずです。
ここからは、過去問演習をくり返しながら、苦手科目の把握と弱点克服につなげていきましょう。
- 実践演習で爆上げ
- 科目別・年度別に過去問を解く ➡ 解説を読んで理解する ➡ 何度も間違えるところをまとめる
くり返し問題を解きながら、自分の苦手なところを把握し、ノートなどにまとめていきましょう。
自分が得意なところは簡単な復習をして、苦手なところをノートでくり返し勉強していきましょう。このノートに書かれているところを克服できれば、合格できる力が身についたことになります。
ステップ③:総復習と弱点克服(10月~12月)
ここまでやってきたことを復習する時期になります。
過去問や模擬問題集を解き、解説を読みながら復習していきましょう。苦手な科目・分野は、特にくり返し取り組み、弱点を克服していきます。
とにかく苦手な科目や何度も間違えるところをノートにまとめ、ひとつひとつ潰していく作業をくり返しましょう。
- 弱点の克服で合格を手繰り寄せる
- 過去問や模擬問題を解く ➡ 解説を読む ➡ 苦手ノートにまとめる ➡ 苦手を潰す
もうひと踏ん張りです。私も苦手な科目があり、取り組むのが嫌になる時期もありました。
でも、ここを乗り切れば限りなく合格に近づくことは間違いありません。
ステップ④:模擬試験の活用と総復習
長かった勉強も残りわずかです。
模擬試験を受けたり、過去問1年分を時間を図って解いてみたりして、試験への準備を進めていきましょう。
この時期は、試験も近いため不安が大きくなってきます。他の人の勉強法や新しい参考書に手を出したくなる時期ですが、ここは自分を信じてやってきた勉強をくり返し行っていきましょう。
- 総仕上げ
- ・体調管理に気をつける
・模擬試験を受けてみる
・新しいものに手を出さない
・自分を信じる
問題演習や解説を読んで理解すること、苦手ノートの復習などやってきたことを信じて、最後まで突っ走りましょう。
過去問の活用法を解説
社会福祉士国家試験の勉強は、とにかく過去問を活用して進めていくのが一番効率的です。
その理由は以下の3つです。
- 出題される問題を把握しながら勉強を進めることができる
- 出題形式が把握できる
- 早い段階で苦手・得意分野を把握できる
前述したとおり、出題範囲が広い中で、テキストを理解してから過去問に取り組もうとすると、膨大な自k何がかかります。
過去問を早い段階で活用することで、試験に出題されやすいポイントを押さえながら勉強することができるため、非常に効率が良いです。
また、これから自分がどの分野に力を入れて勉強するべきなのかも分かります。
社会福祉士国家試験は、とにかく範囲が広いので、過去問を活用した勉強をして、効率的に取り組む必要があります。
勉強を継続するコツ
試験までは長い道のりとなります。
常にモチベーション高く、意欲的に勉強に取り組むのは難しいと思います。実際に私もそうでした。
ここでは、私が社会福祉士国家試験の際に実践し、その後のいろいろな資格試験でも実践した、「勉強を継続するコツ」をお伝えします。
ポイントは以下の3つです。
- 自分は社会福祉士国家試験に合格すると宣言する
- 少しでも取り組めた自分を褒める
- 夜は寝て、朝早く起きる
それぞれ詳しく解説します。
勉強のコツ①:自分は社会福祉士国家試験に合格すると宣言する
ひとつ目は、「自分は社会福祉士国家試験に合格すると宣言する」です。
これは、家族や友人などの周囲の方々に、「自分は社会福祉士国家試験に合格します」と宣言する方法です。
「受験する」ではなく「合格する」と宣言するのがポイントです。
これにより、自分自身を勉強しなければならない環境に置くことになります。
「とりあえず受験してみよう」「どうせ受からないと思うけど…」という意識の人は、実際合格するのは難しいです。長期間の勉強に耐えるメンタルが身についていない状態だからです。
先に落ちた時の言い訳を作っている人は100%合格しません。自信がなくても良いので、「自分は合格する!」と宣言してしまいましょう。
勉強のコツ②:少しでも取り組めた自分を褒める
勉強を始めたころや勉強を続けていると、どうしてもモチベーションが上がらず、勉強したくない気持ちに襲われることが何度もあります。
そんな日は、「テキストを触る」「1問だけ解いてみる」といった小さなことでも良いので、取り組みましょう。そして、そんな絶不調の日でも勉強したという素晴らしい自分を褒めてあげましょう。
社会福祉士国家試験は、大学受験などと違って自分が合格点に届けば合格できる試験です。つまり、自分との戦いであり、自分をどれだけ認めて、信じてあげられるかということが大切になります。
毎日少しでも良いので、継続することを意識しましょう。
勉強のコツ③:夜は寝て、朝早く起きる
生活習慣を整えることで、勉強効率を上げることができます。
当然ながら試験は夜中ではなく、日中に行われます。その時間帯に合わせて勉強することが重要です。
また、夜は脳が疲弊している状態であるため、朝に比べて勉強効率が格段に下がります。
生活習慣をきちんと整えることは、勉強を行う上では必須となります。
まとめ
今回は、社会福祉士国家試験合格のためのロードマップについて解説してきました。
4月から勉強を始めれば、ある程度余裕を持って勉強に取り組めると思いますが、それ以降でも十分チャンスはありますので、ぜひ社会福祉士取得を目指す方は、最後まであきらめずに頑張っていきましょう。